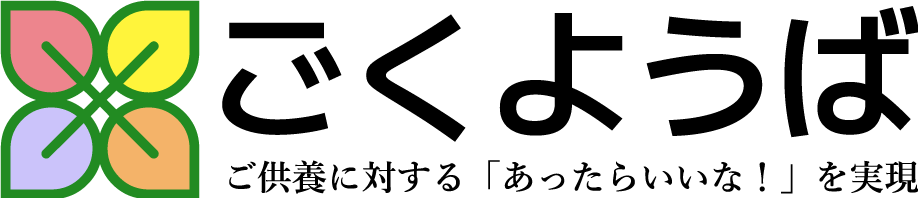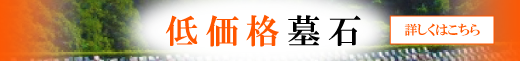ご家族が亡くなったとき、悲しみと同時にすぐに考えなければならないのが「葬儀のタイミング」です。
「いつ通夜を行えばいいのか」「火葬はどの段階で?」「納骨は四十九日?」など、人生でそう何度も経験しないからこそ、分からないことばかりです。
葬儀は宗教・地域・火葬場の予約状況などによって日程が左右されることも多く、「常識通り」にいかないケースもあります。
この記事では、一般的な葬儀の流れとスケジュール、タイミングを決める際の注意点、柔軟な対応が求められる場面などを、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
一般的な葬儀の日程・スケジュール感
多くの家庭では、亡くなった当日〜4日後を目安に通夜・葬儀が行われます。
以下は、平均的なスケジュールのイメージです。
| 日数 | 内容 |
|---|---|
| 1日目 | ご逝去 → 死亡診断書の取得・連絡 |
| 2日目 | 葬儀社との打ち合わせ・納棺 |
| 3日目 | 通夜 |
| 4日目 | 葬儀・告別式 → 火葬 |
| 四十九日頃 | 納骨・法要 |
このスケジュールはあくまで目安であり、地方によっては火葬を先に行う「前火葬」形式をとる地域や、火葬まで1週間待つ必要がある都市部もあります。
「何日以内にやらなければいけない」という明確な期限があるわけではありませんが、亡くなった日から数日以内に火葬するのが一般的です。
逆に、法律(墓地埋葬法 第3条)では、ご逝去から24時間経過するまでは火葬が禁止されています。
火葬場の予約状況がタイミングを左右する
特に都市部では、火葬場の混雑が葬儀のタイミングを左右する最大の要因です。
人気のある火葬場では3〜4日待ちになることもあり、それにあわせて通夜・告別式の日取りを調整する必要があります。
このため、葬儀社に依頼すると、まず最初に「火葬場の空き状況」を確認し、その日程を軸に通夜や式の日取りを決めていく流れが一般的です。
特に年末年始やお盆、彼岸の時期などは混雑しやすく、日程の調整に柔軟性が求められることもあるので注意が必要です。
宗教・宗派による違い
葬儀のタイミングは、仏教・神道・キリスト教など、宗教や宗派によっても異なります。
- 仏教(特に浄土真宗・曹洞宗など):通夜 → 葬儀 → 火葬 → 四十九日納骨が基本
- 神道:通夜の代わりに「通夜祭」や「遷霊祭」が行われる
- キリスト教:通夜はなく、前夜式や告別式が中心になるケースも多い
僧侶・神父・神主など、宗教者の都合も調整に必要な要素です。
法要の希望日があれば、早めに相談しておくと安心です。
葬儀のタイミングを決めるときの注意点
葬儀は、形式も大切ですが、何より「誰が、どのように送るか」が重要です。
日程を決める際には、以下の点に注意しましょう。
1. 参列者の都合
遠方から来る親族がいる場合、平日より週末が良いことも。急ぎすぎると参列できない人が出ることもあります。
2. 火葬・式場の空き状況
人気の式場や火葬場は予約が取りづらく、希望通りにならないケースもあります。
柔軟に対応できるようにしましょう。
3. 日取りへのこだわり
仏滅・友引などを避ける方もいますが、最近は気にしない方も増えています。
僧侶や家族で意向を確認しておきましょう。
4. 菩提寺や宗教者との調整
葬儀の読経・法要を依頼する場合は、宗教者のスケジュールも早めに確認しておく必要があります。
やむを得ない事情で日程がズレる場合もある
最近では、家族葬や一日葬など、形式が多様化しており、「逝去から1週間後に火葬のみ行う」「家族だけで通夜と火葬だけ行い、葬儀は後日」など、ケースに応じた柔軟な対応が広がっています。
また、逝去のタイミングが深夜であったり、年末年始・大型連休中で行政手続きが遅れる場合などは、火葬や式のスケジュールも後ろ倒しになることがあります。
大切なのは「形式にとらわれすぎず、故人を心を込めて見送ること」です。
「いつやるか」より「どう送るか」
葬儀のタイミングに“正解”はありません。地域や宗教の習慣も大切ですが、それ以上に大事なのは、遺族や参列者が無理なく、そして心を込めて見送れる環境を整えることです。
日程に不安があるときは、葬儀社や宗教者に早めに相談し、現実的なスケジュールを立てましょう。
ご家族や親族との連携も忘れずに。
「ごくようば」では、葬儀後の納骨やお墓探しに関する情報も多数掲載中。
葬儀が終わったあとの供養についても、安心して選べるお手伝いをしています。