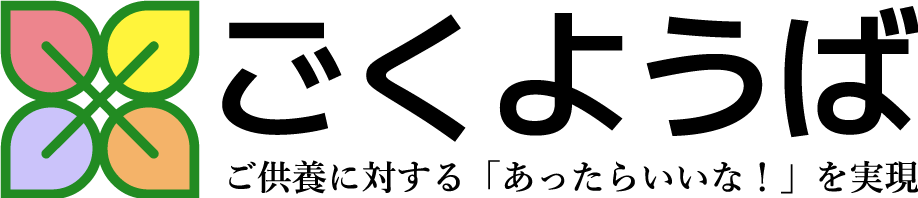お墓参りは、「いつ行くのが正しいのか」「決まりがあるのか」と迷う方も多いのではないでしょうか?
実は、お墓参りに“絶対にこの日でなければいけない”という厳格なルールはありませんが、故人を偲ぶ大切なタイミングとして、古くから親しまれているいくつかの節目があります。
ここでは代表的な時期を紹介しながら、それぞれがどんな意味を持っているのかもあわせて解説していきます。
お墓参りはいつ行くの?

祥月命日(しょうつきめいにち)
祥月命日とは、故人が亡くなった“月と日”が同じ日のことを指します。
たとえば、8月15日に亡くなった方の祥月命日は毎年「8月15日」となります。
この日は、故人の命日そのものであり、特に丁寧に供養するべき日とされています。お墓参りに行くほか、仏壇に手を合わせたり、お花やお供え物を準備する方も多いです。
法要(1周忌、3回忌など)を行うタイミングでもあり、親族が集まることも多い重要な節目です。
月命日(つきめいにち)
月命日とは、故人が亡くなった“日”と同じ日を毎月の供養日とする考え方です。
例えば、8月15日が命日であれば、毎月15日が月命日となります。
特にご家族や近しい方にとっては、月命日に仏壇やお墓へお参りすることで、日々の中でも故人とのつながりを感じることができます。
月命日にお墓参りを欠かさないという家庭もありますが、無理のない範囲で気持ちを込めて手を合わせることが大切です。
お彼岸
お彼岸は、「春」と「秋」の年2回訪れる、日本独特の供養期間です。
春分の日・秋分の日を中心に、それぞれ前後3日間を含めた計7日間が“お彼岸の期間”とされ、お墓参りをする方が非常に多くなります。
お彼岸ってどういう意味?
お彼岸とは、仏教における“彼岸(あの世)”に思いをはせ、現世(此岸=しがん)から故人に祈りを届ける期間とされています。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉にあるように、季節の節目としても知られています。
春のお彼岸は3月20日前後、秋のお彼岸は9月23日前後に訪れ、宗教や宗派を問わず多くの家庭でお墓参りが行われる時期です。
お盆
お盆は、故人の魂がこの世に帰ってくるとされる期間で、祖先を供養する一大行事です。
地域によって異なりますが、一般的には8月13日〜16日頃に行われることが多く、帰省にあわせてお墓参りをする人も多く見られます。
お墓参りのタイミングとしては、お盆の初日(迎え火)または最終日(送り火)に行くのが一般的とされます。
この時期はお墓の清掃や花の交換、提灯の飾り付けなども一緒に行うことが多く、親族で集まる良い機会でもあります。
年末年始
年末年始は、1年の締めくくりや新年のスタートに際して、お墓参りをする方も増えています。
「1年間無事に過ごせたことへの感謝」や「新しい年も見守ってください」という気持ちを伝える意味合いが強く、特に決まった日取りはありません。
年末の大掃除とあわせてお墓の清掃をする家庭もあり、年末年始を通じて家族の絆を深める大切な時間にもなります。
お墓参りに行ってはいけない日はあるの?

結論から言うと、お墓参りに“行ってはいけない日”というものは存在しません。
ただし、一部の地域や世代によっては、以下のような考えが根強く残っている場合があります。
これらはあくまで“縁起や習慣の話”であり、マナー違反というわけではありません。
大切なのは「どの日に行くか」よりも、「故人を思う気持ち」を大切にすることです。
お墓参りの時間帯
お墓参りの時間にも決まりはありませんが、日中の明るい時間帯(午前10時〜午後4時頃まで)に行くのが一般的です。
これは以下のような理由からです。
- 管理事務所や水場の利用時間に合わせる
- 明るい方が安全(足元の段差や石など)
- 他の参拝者にも配慮できる
また、夏場は暑さを避けて朝のうち、冬は寒さや日没を避けて昼前後など、季節によって調整すると快適です。
お墓参りに持っていく物
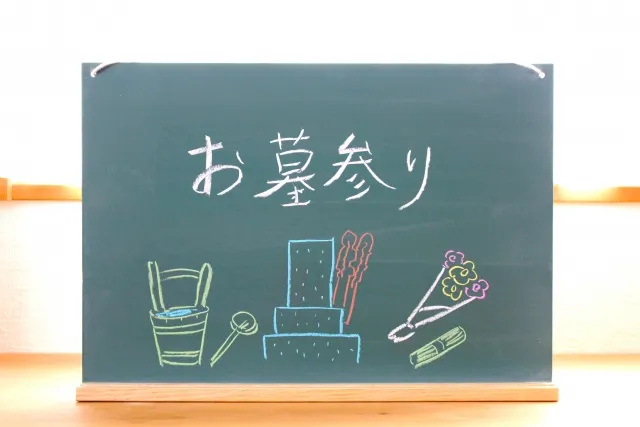
お墓参りに必要な持ち物は、地域や宗派によって多少異なることもありますが、基本的には以下の通りです。
| 持ち物 | 用途 |
|---|---|
| お花 | 故人を供養するため。対で飾るのが基本 |
| お線香 | 焼香用。ライターやチャッカマンも忘れずに |
| お供え物 | 故人が好きだったもの(食べ物・飲み物など) |
| 掃除道具 | ほうき・雑巾・バケツ・手桶など |
| 数珠 | 仏式の方は必携 |
その他、夏場なら虫除けスプレー、冬場は手袋など、季節ごとの準備もあると安心です。
まとめ
お墓参りに決まったルールはなく、故人を偲ぶ“気持ち”が何よりも大切です。
とはいえ、お彼岸やお盆、命日などは気持ちの区切りをつけやすく、ご先祖様への感謝や祈りを伝えるよいタイミングといえるでしょう。
また、「行ってはいけない日」などの迷信にとらわれすぎず、自分と家族にとって無理のない日程・時間帯で行うことが大切です。
ごくようばでは、納骨後のお参り情報や、墓地・霊園ごとのお参りのしやすさも紹介しています。
これからお墓を探す方は、「お参りしやすさ」も一つの判断基準として、ぜひ活用してみてください。