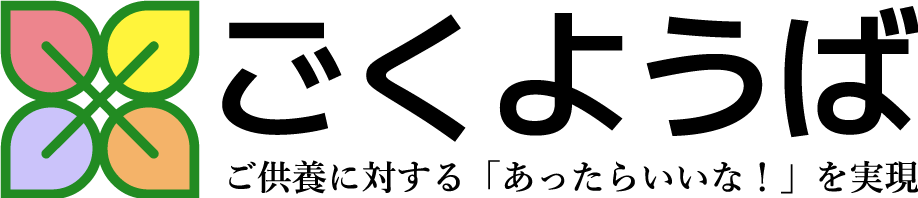親や配偶者が亡くなったあと、実家のお墓をどうすべきか悩む人が増えています。
「このお墓、誰の名義になってるの?」
「相続登記って必要なの?」
「名義変更しないと何が起こるの?」
墓地の名義変更や手続きは、意外と知られていない落とし穴がたくさんあります。
放置すれば、供養ができない・改葬や墓じまいができないといった問題にもつながります。
本記事では、墓地の名義変更の基礎知識から手続き方法、相続登記との違い、注意点まで丁寧に解説していきます。
墓地の「名義」とは何か?

墓地には、基本的に1人の“名義人(使用者)”が設定されており、墓地の使用権を管理する責任者として扱われます。
- 「所有権」ではなく、「使用権」であることが多い
- 寺院墓地や民営霊園では、墓地使用契約書に基づいて名義が管理されている
- 名義人は管理料の支払い義務・供養や移転の判断権限を持つ
つまり、「名義人が不在」の状態は、そのお墓の運用や供養が“宙ぶらりん”になるリスクがあるということです。
名義変更が必要なタイミングとは?
| ケース | 名義変更が必要な理由 |
|---|---|
| 名義人が死亡した | 使用権の継承者が明確でないと、管理者が判断できなくなる |
| 墓じまい・改葬を検討している | 契約者本人でないと、改葬許可申請などの手続きができない |
| 複数人が口出しして揉めている | トラブル防止のため、1人の代表使用者を明確にしておく必要がある |
墓地の名義変更と「相続登記」の違い
混同されやすいのが、墓地の名義変更と不動産の相続登記です。
| 項目 | 墓地の名義変更 | 不動産の相続登記 |
|---|---|---|
| 登録対象 | 墓地使用権(所有権ではない) | 土地・建物などの所有権 |
| 法的義務 | 明確な義務はないが、放置はトラブルのもと | 2024年4月から相続登記が義務化 |
| 管理者への届け出先 | 寺院、霊園の管理事務所 | 法務局(登記所) |
| 書類・手続きの難易度 | 比較的シンプル | 法律の専門知識・戸籍書類などが必要 |
墓地の使用権は「祭祀財産」として民法897条に基づいて特別な相続扱いになります。
遺産分割と切り離して考える必要があります。
墓地の名義変更手続きの流れ

名義変更は霊園や寺院によって必要書類が異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。
①霊園・寺院に名義変更の申し出
- 電話や窓口で「名義変更をしたい」と相談
- 必要書類・手数料の案内を受ける
②必要書類を準備
| 書類例 | 解説 |
|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 継承関係(血縁関係)を確認するため |
| 使用許可証(使用承諾書) | 墓地契約時の書類(紛失していても再発行可) |
| 誓約書・申請書 | 霊園・寺院が用意する書式への記入 |
| 印鑑証明・住民票 | 現名義人(故人)と継承者の住所確認用 |
③名義変更手数料の支払い
- 金額は霊園によって異なる(数千円〜数万円が目安)
④書類提出・名義変更完了の通知
- 正式に継承者として登録され、今後の連絡・管理料請求先が切り替わる
名義変更せずに放置した場合のリスク
トラブルを避けるためにも、亡くなったらすぐに名義変更の相談を始めるのがベストです。
名義人を「誰にするか」で迷ったら…
- 祭祀を主に担う人(長男に限らない)が基本とされます
- 実際は、「管理料を払えるか」「距離的に通えるか」など現実的な要素で選ぶのが妥当
| ケース | 選任のヒント |
|---|---|
| 兄弟が複数いる | 代表者を一人立てて、家族で合意形成をしておく |
| 跡継ぎがいない | 永代供養墓へ移行し、管理不要な形にしておく |
| 法的なサポートが必要 | 家族信託や専門家(行政書士・弁護士)を活用 |
まとめ|墓地の名義変更は“供養のバトン”をつなぐための準備

名義変更を後回しにしていると、
「誰が責任を持つのか分からない」
「供養したいけど手続きが進まない」
といった問題が一気に顕在化します。
そして、名義変更を機に今後のお墓の方向性(改葬・永代供養・墓じまい)も検討しておくと、家族全体が安心して供養を続けられます。
▶︎ 全国の霊園・永代供養墓・納骨堂を探す(ごくようば)
ご家族に合ったスタイルを、早めに探してみましょう。