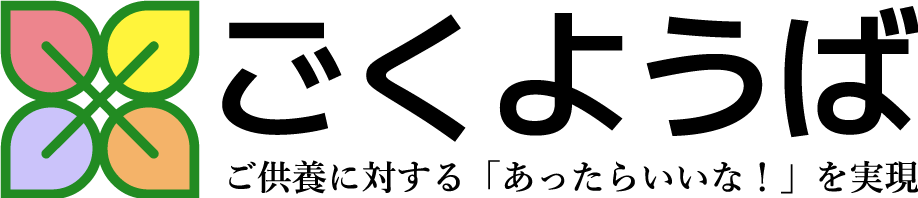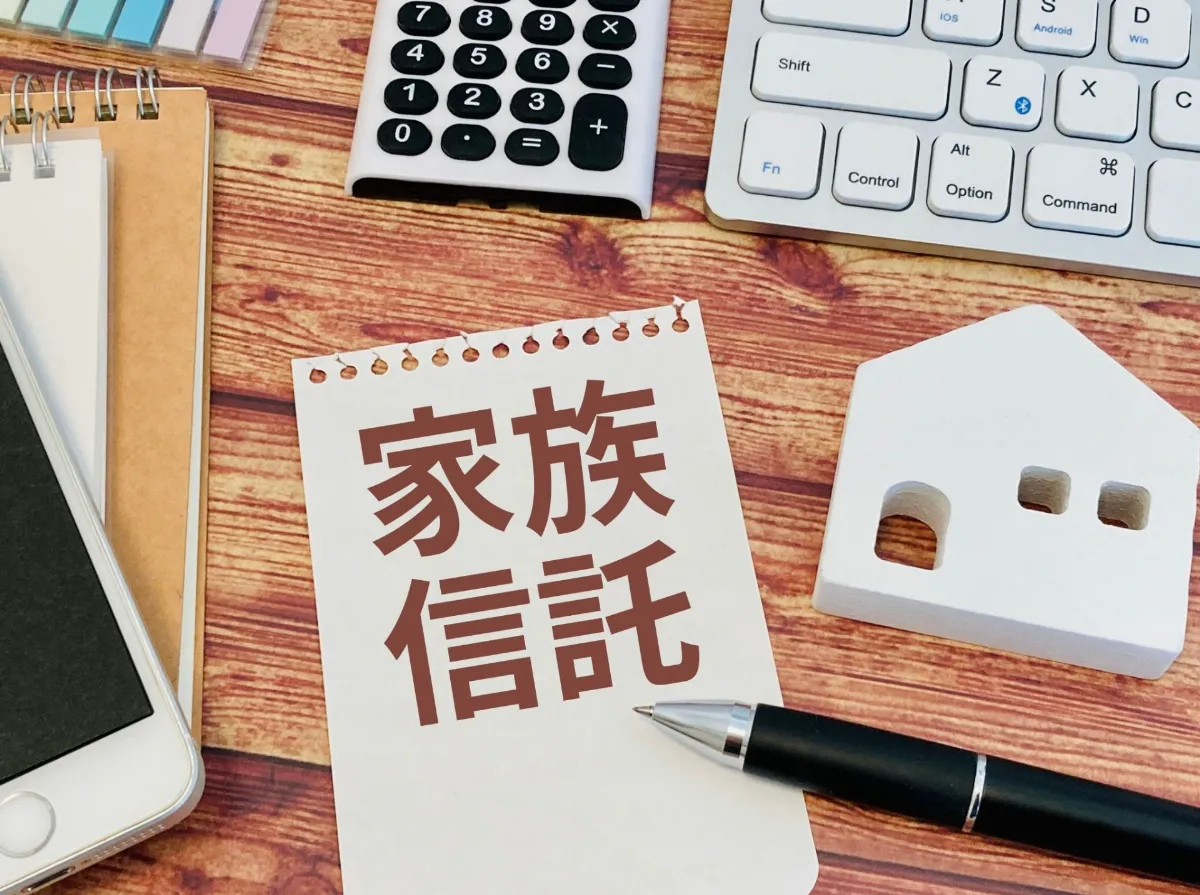人生の終盤に近づくと、お墓や供養のことが気になるものです。
「子どもがいない」「親族と疎遠」「相続トラブルを避けたい」など、現代ならではの悩みに対応できる手段の一つとして注目されているのが「家族信託」です。
この記事では、家族信託で“お墓問題”に備える方法について、仕組みや活用例、遺言・成年後見との違いも交えて詳しく解説します。
家族信託とは?基本のしくみ

家族信託とは、信頼できる家族などに自分の財産の管理・運用・処分を任せる制度です。
特に認知症や判断能力の低下を見据えた「備え」として活用されることが増えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人(本人) |
| 受託者 | 財産の管理・運用を任される人(子など) |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人(通常は委託者自身) |
例えば、「自分が元気なうちは自分で管理し、認知症になったら子どもが管理する」といった設定ができます。
家族信託とお墓の関係性
お墓そのものは“祭祀財産”として扱われるため、金銭的価値よりも「供養」の意味が重視されます。
そのため、相続や贈与の対象にはなりにくく、一般的な財産とは異なる位置付けになります。
しかし、お墓の管理費用や墓地の使用権、永代供養料など、「お墓に関するお金」は通常の財産と同じく信託に組み込むことが可能です。
こんなニーズに対応できます
実際に使える家族信託の例
例1:永代供養を依頼したいケース
例2:管理費支払いを続けてほしいケース
例3:ペットと一緒の納骨を希望するケース

家族信託と遺言・成年後見の違い
| 比較項目 | 家族信託 | 遺言 | 成年後見 |
| 主な目的 | 財産の管理・承継 | 死後の財産分配 | 判断能力を補う |
| 効力発生時 | 生前から有効 | 死後に有効 | 判断能力が低下したとき |
| 柔軟性 | 高い(個別契約で設定自由) | 限定的 | 制限が多い |
| お墓管理に使えるか | ○(費用面で可能) | △(死後の希望のみ) | ×(財産管理限定) |
家族信託は「生前から設定できる」点が最大のメリットです。
特にお墓や供養は“死後のこと”である一方、準備自体は元気なうちに済ませたいというニーズに合っています。
家族信託を使う際の注意点

信託契約書は司法書士や信託専門家のチェックを受けることが望ましいです。
まとめ|お墓の安心を「見える形」で託す方法
お墓や供養に関する不安は、精神的にも大きなストレスになります。
家族信託を活用すれば、自分の希望を具体的に契約として残すことができ、家族に迷惑をかけずに済む可能性が高まります。
- 永代供養や管理費の支払いも信託で可能
- 遺言や成年後見よりも柔軟に設定できる
- お墓の問題は“金銭面”で整理しておくのが有効
終活の一環として、家族信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ごくようばでは、永代供養・管理の負担が少ない霊園も多数掲載中!
▶︎ 全国の永代供養・お墓を探す